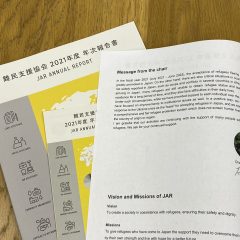難民が、地域社会の中でつながりを持ち、
ともに暮らしていける関係性を
築けるよう
支援します。
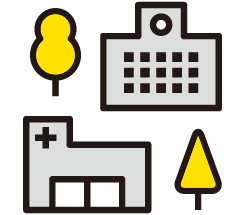
日本での生活が長い場合でも、地域社会から孤立してしまう難民は少なくありません。
難民支援協会(JAR)は、自治体、学校、病院など、地域社会をつくる人びとと難民を橋渡しし、難民が社会の一員として地域のなかでつながりを持ち、ともに支えあって暮らしていけるよう支援しています。
| 事業内容 |
|
|---|---|
| 協働先 |
|
地域関係者との連携・
難民 / 難民コミュニティ
への支援
約1,200人
2022年度実績
事業紹介
脆弱性の高い難民の不安に寄り添う持続的な支援

企業からいただいた飲食料品を難民の方に配る様子
コロナ禍の影響は脆弱性の高い人々には特に尾を引いて残ります。難民も、以前はコミュニティ内で助け合いに努められていても、時間が経つごとに、個人や各世帯の相互支援の余力は先細り、自身の生活を守ることで手一杯です。経済的困窮から「家族に食べ物がない」という声や、 無料PCR検査場の減少や解除で健康状態の確認が難しくなり、周りに体調不良者が出るたびに「自分は大丈夫だろうか」と大きな不安にかられる状況もありました。 難民が地域で命を落とすことなく安心して生活できるように、フードバンクや医療機関、行政、社会福祉協議会、地域の企業や団体と協働し、新宿区や埼玉県川口市をはじめ複数自治体で、飲食料品、衛生用品やマスクの配布など約180件の支援を行いました。
地域関係者間での連携強化と開拓に向けて

学生に対し、地域支援手法について勉強会を実施
特に難民が暮らす地域では、多様な地域関係者が連携しあうことが欠かせません。難民の方が抱える課題は、在留資格、経済的困窮、医療、子ども支援など多面的であり、またそれらが関係しあうため、1つの課題に向き合うだけでは解決ができないためです。例えば、病気を抱える難民の方を医療機関に紹介すると同時に、生活のほかの面を支えるために医療機関とフードバンクをつなぎ、JARは在留資格の手続き面を担うなどが必要とされます。そこで、埼玉県川口市・越谷市、千葉県佐倉市、茨城県常総市、東京都内の複数区、また東海地方でも、支援関係者向けに難民を取り巻く現状についての勉強会やアドバイスを215回にわたって実施し、地域支援の開拓や継続的な関係構築に務めました。
※ 2022年度年次報告書より