
2023.11.21
ブラジルから来て20年。「日本育ち」の子どもに寄り添うミヤワキ・シズカさんの挑戦
*本記事には同内容のポルトガル語版もあります(ニッポン複雑紀行で初の二言語記事の試みです)/ Segue o link do artigo em português. > 20 anos no Japão. O desafio de Shizuka Miyawaki que se acompanha as crianças que “crescem no Japão”
静かに増えていく「日本育ち」の子どもたち
名古屋市から北西30キロほどの位置にある岐阜県大垣市。
周辺には自動車関連などの様々な工場があり、1990年代前後からブラジルにルーツを持つ人々が暮らすようになった。
バブル景気に沸く日本社会は1990年施行の改正入管法でブラジルなどから日系人の受け入れを拡大し、その多くは工場での不安定な労働に組み込まれた。

その時代からすでに30年以上が経つ。
当然の帰結として、今では自らブラジルから移住してきた1世だけでなく、子どもの頃に親と一緒に来日した子どもや、日本で生まれた子ども(1.5世や2世以降)がかなり多くなった。
大垣市では外国籍住民が全体の4%弱を占め(全国平均が2%強)、その4割ほどがブラジル国籍で最多となっている。短期の「デカセギ」ではなく、世代を重ねた「定住」が静かに進んでいる。
かれらは「いつか帰る人たち」ではない。日本で生まれて、日本で学んで、日本で生きていく。そうした「日本育ち」の子どもたちの現実は見えづらく、だからこそ伝えていきたいと思う。



例えばソフィアという日本生まれで10歳の女の子がいる。
*これ以降本記事で取り上げる子どもは全て仮名で、プロフィールやエピソードにも一定の加工を施している
ソフィアの父は自らの両親(ソフィアの祖父母)に連れられ、10歳のときにブラジルからやってきた。「日本の学校」に中学まで通い、そのあと働き始めた。今は解体工事の現場で仕事をしているという。
最初に来日した祖父母から数えて3世代目にあたるソフィアも、最初は子ども時代の父と同じく日本の小学校に通っていた。だが「将来ブラジルに帰るかもしれない」という親の考えもあって、ポルトガル語で学べる「ブラジル学校」に転校したという。
ブラジルルーツの人々が多い愛知や岐阜などの東海地域には、大垣も含めて一定数のブラジル学校がある。

将来ブラジルに帰るか、それともこのまま日本にとどまるか。すでに日本で過ごした時間のほうがはるかに長いソフィアの父親は、私の質問に日本語でこう答えた。
「色々あって(ブラジルに帰るという)考えがどんどん変わっていったんです。それで(娘をブラジル学校から)日本の学校へ戻そうかと思ったんですけど、本人が『ブラジル学校がいい』って言うので。だから、日本語を忘れないように公文も習っとるんです」
日本の学校、ブラジル学校、公文。こうした教育環境で育ったソフィアは、ポルトガル語も日本語もスラスラと話す。

だが、ルーツの近しい子どもたちの中でも、一人ひとりの状況は様々だ。
どちらかの言語が不自由な子もいるし、両方の言語で問題を抱える子もいる。また、ソフィアのように一見問題なく二つの言語で会話ができていても、それらが学習言語としても育っているとは限らない。
ブラジルと日本との間でアイデンティティに悩む子たちもいる。ブラジルに行ったことがない場合も多い。日本の学校に行くか、ブラジル学校に行くか、親も子も悩む。

互いのことを避け合う子どもたち
私はソフィアと「エスパシン(EspaSim)」で出会った。大垣で8年前にできた「アフタースクール」だ。
昼間は日本の学校やブラジル学校に通う子どもたちが、毎日の放課後ここにやってくる。最近では、学校自体から離れる子どもも目立つようになった。
ブラジルルーツの子が大多数だが、限定しているわけではない。日本とベトナムの子も一人ずつ通っている。
居場所を作り、学校の宿題を手伝い、コミュニティに教育の大切さを伝える。大事にしているのは、一人ひとりの気持ちや感情を丁寧に受け止めること、自尊心やアイデンティティを育んでいくことだ。


エスパシン(EspaSim)はポルトガル語の「espaço(場所)」と「simplificar(シンプルにする)」から来ている。家庭で、学校で、職場で、子どもや親たちが直面する日々の困難をほどく場でありたい。そんな思いが込められた名前だ。
このアフタースクールを2015年に作ったのはミヤワキ・シズカさん。2002年、当時18歳だったシズカさんは、先に日本で働いていた父を追って、ブラジルから来日した。
シズカさんも最初は工場で働いたという。いずれブラジルに戻るつもりだったが、日本で結婚し、3人の娘が生まれ、生活のベースは日本になっていった。3人ともブラジルにはまだ行ったことがない。

彼女が日本でブラジルルーツの子どもたちに関わり始めたのは、まだ自分の長女が幼い頃だった。理想的な保育所が見つからず、アパートの一室に自分でつくったそうだ。ほかの家庭の子どもも5人ほど預かっていたという。
シズカさんにはブラジル学校で働いた経験もある。2008年に日本からブラジルの通信制大学に入って教育学を学び、教員資格を取った。私が彼女と出会ったのはその翌年のことだ。在日ブラジル人が一時的に30万人を超えた2000年代、日本各地のブラジル学校では教員有資格者の確保が広く課題となっていた。
エスパシンは2015年に邑井ジェニーさんという女性と二人で立ち上げた。ジェニーさんは大垣の小中学校で支援員として働いていて、その中でブラジルルーツの子どもたちが直面する様々な困難を目にしてきたという。

だがエスパシンの立ち上げ直後、ジェニーさんは突然病気で亡くなってしまう。かけがえのないパートナーを失い、シズカさんは絶望した。
「日本の学校の宿題は彼女が、ポルトガル語に関することは自分が分担するはずだったのに…。日本語が不得意な自分がやりきれるだろうか」
*これ以降のインタビューはポルトガル語からの翻訳、そうでない場合はその旨を記す
けれども、すでにエスパシンにはハファエウという小学2年生の男の子が通い始めていた。目の前にいたこの一人の子どものためにも、やめるわけにはいかない。そう思ったシズカさんの中で、力が湧いてきたという。

日本の小学校に通うハファエウは、学校ではエスパシンに通っていることを隠して過ごしていた。
「ハファエウが小学校でわからないことがあって質問をしたら(先生から)『そうか、ブラジル人だから仕方がないね』と言われ、その経験が『ブラジル人であることは劣っている』というイメージを彼に植え付けてしまったらしいんです」
「ハファエウのお母さんは彼にブラジルルーツを否定せずに生きてほしいと思って(エスパシンに)通わせていたけど、ハファエウはブラジルに関わることは覚えようとせず、学校では同級生に知られないように気を使い、友達には塾に行っていると言って、エスパシンのことは秘密だった」
「彼は日本が大好きで日本的なものの考え方がとてもよくわかったけれど、ブラジルのほうはわからなくて否定するようになってしまったんです」


シズカさんは、親の転勤で岐阜を離れたハファエウと最近になって再会したという。エスパシン8周年のパーティーに、母親と一緒に二人で来てくれた。当時は小学生だった彼も今や高校生だ。
「(そのとき)彼はこんなふうに言ったんです。『ブラジル人が日本人グループに近づこうとすればある種の尊重はされるけど、それは真面目な尊重じゃなくて、なんちゃっての(表面的な)尊重なんだ』って」
「『ブラジル人はブラジル人同士、日本人は日本人同士でいたらいい。ブラジル人が日本人と友だちになりたかったら、日本人と同じようにしないとダメなんだ』って。重いと思いませんか? 悲しいですよね。彼の言ったことが忘れられない。こういうことが積み重なって自尊心が削がれていくのだと思う」
ハファエウは日本社会で、学校で、どんな経験をしてきたのだろうか。シズカさんと話していると「自尊心」という言葉がよく出てくる。彼女が子どもたちと向き合う中で大切にしていることだ。ルーツもその重要な一部なのだと思う。


現在エスパシンに通う小学校中学年のマリアは、かつてハファエウが卒業したのと同じ学校に毎日通学している。
ある日シズカさんが学校まで彼女を迎えに行ったとき、マリアは南米の別の国をルーツとする同級生から「もう話しかけてこないで」と言われた話をした。彼女はこう言ったという。
「(話しかけてほしくないのは)私がブラジル人で、ポルトガル語を話すからなんだって。日本人はここでポルトガル語や他の言葉を話す人を下に見ていて、そういう人と話すと自分もそう思われちゃうからだって」
シズカさんが「それであなたはどう思ったの?」と聞くと、マリアは「かわいそうだよね、そういうふうに周りから聞いて彼がそう信じるなら、本当にそうなっちゃう」と答えた。
一人ひとりの子どもたちが現実に直面し、その中で自分なりの答えを出そうとしている。シズカさんは毎日、かれらが発する言葉に真剣に耳を傾ける。

小学校高学年のパウリーニョという男の子も、昼間は日本の学校に通学している。
彼が学校で使う色々な持ち物には名札がついていて、そこには「パウリーニョ」とは別の日本名が書かれている。
彼の家族がブラジルから日本に移って20年以上が経つ。年齢の離れた二人の姉はブラジル生まれで、パウリーニョだけが日本生まれだ。
日本の学校を卒業した姉たちはポルトガル語があまり得意ではなく、弟には自分たちと違って二言語で育つチャンスを与えたいと願っている。

そんなパウリーニョを見ながら、シズカさんは言う。
「パウリーニョは学校ではブラジルルーツの友だちとほとんどしゃべらないの。ここでの彼の様子をみていればわかるけど(ブラジルが)嫌いじゃないのに学校では話さない」
「どうしてだと思う? そうしないと周囲からの扱いが変わるから。自分に対する扱いが変わらないように、彼は学校では異質な(外国ルーツの)友だちを避けている」
クラスの中での眼差しを内面化し、外国ルーツの子ども同士が「異質な存在」として互いのことを避け合う。そんな現実がある。

シズカさんと共にエスパシンを運営するオオシロ・ニュートンさん。彼には工場での仕事をリーマンショックで失ったあとに、東京の語学学校で英語の講師を勤めていた時期があった。その頃、16歳の生徒が自ら命を絶った。
「彼はハーフ(日系と非日系の両親)のブラジル人でした。ごくふつうの若者でした。だけど、大人になるにつれ降りかかってくる重みや感情的なフラストレーションへ対処する術を備えていなかったのかも…」
「日本に暮らすブラジル人子弟の、特にこの新しい世代の問題というのは…。僕たちはもうデカセギの第3、第4のサイクルを生きていますよね」
「この世代はどんどん脆くなっていると感じるんです。なぜかというと、日本で生まれ育った、確固たるアイデンティティ形成ができていない世代の子どもだから」

「日本育ち」のすべての子どもたちが安心して生きられる場所であるために、この社会はどう変わらなければならないのだろうか。
親の労働と子どもの送迎
エスパシンでは一日に何度か送迎の時間がある。
付近に同様の施設がないため、利用者宅は広範囲に拡散しており、それぞれの家庭ごとに時間帯のニーズも様々だ。シズカさんやほかのスタッフが手分けして送迎車を走らせる。

基本的な流れとしては、下校時間後の夕方に地域の学校を順に回って迎えに行き、エスパシンでの時間を過ごして、夜にそれぞれの自宅まで送り届ける。仕事終わりの親がエスパシンまで迎えに来るケースもある。
私たちが訪れたときは春休みで学校がなかった。そのため早朝の6時台から送迎が始まった。親たちの多くは工場での派遣労働などに就き、出勤時間がとても早いからだ。エスパシンによる子どもの送迎に、会社による親自身の送迎が相次ぐ場合もある。
ブラジルルーツの親子においては、日本における親の不安定な労働のあり方に、子どもたちの生活が大きな影響を受ける場合も少なくない。仕事の変動に合わせ、引っ越しを繰り返す家庭もある。子どもたちの姿の背後には、親たちの苦悩と努力が見え隠れする。
そんな親子での「送迎」の場で、娘がエスパシンに通うシングルマザーの女性からお話を聞いた。


――どんなお仕事をされているんですか?
アルバイトでパチンコ部品の組み立てをやっています。(工場が)少し遠いところなので帰りが遅くなって娘の送迎も最後のほうになるんです。だけどエスパシンが大好きみたいで、たまに仕事が早く終わって迎えに行くと「帰りたくない」と言って泣きます。
――日本はもう長いですか?
最初に来たのは2008年でした。娘もまだいなかった。日本に来たら不況(リーマンショック)が来て、3年後にブラジルへ戻りました。すぐに日本へ戻ってくる予定だったけど、2011年に震災が起きて、私のビザが取り消されてしまった。
だからブラジルに残って仕事を見つけて、そのまま9年ブラジルで過ごしました。結婚して、娘が生まれて、夫と別れました。ブラジルでは一人で子どもを育てられないと思って、また日本に来ました。

――シングルマザーになって、娘さんのために日本に戻ってこられたんですね。
日本に戻ってきた最初の頃は、食べさせるものがなくてご飯に塩を振って出すこともありました。
「私はシングルマザーです」と伝えたとき、派遣会社は「大丈夫」と言いました。娘の面倒を見てくれる人が自分のほかにいないけど、「大丈夫、大丈夫」って言われたから来たんです。
でもここに着いたら2ヶ月間小さなワンルームに入れられて、仕事をもらえなかった。「お金がないし、この子を食べさせるのに働かなくちゃいけないんだ」と訴えました。この子がいるからって。
2008年の頃の友人たちに助けてもらって、なんとかその2ヶ月を乗り切りました。

――事前の約束と話が違っていたんですね。
派遣会社は(最初の生活費として)4万円くれたけど、それはあとで返金しないといけないものでした。仕事を紹介してくれないのにお金を戻さないといけなかった。
今も日本に来たときの航空券代を払わないといけないんだけど、仕事を紹介するという約束を果たしてくれなかったので、返さなきゃいけないのはわかっているけど、払えるときにしか払いませんと伝えてあります。
大抵の派遣会社は私が6歳の娘がいるシングルマザーと言えば「ああ、だめ」と断ります。私のように小さい子がいるひとり親は雇われないから難しいんです。

――娘さんがエスパシンに通い始めたきっかけを教えてください。
元々はブラジル学校に行っていたんですけど、学校へ行きたがらなくなっちゃったんです。公園に遊びにいくこともないし、先生たちとの双方向的な交流もなくて。だんだんと楽しくなくなってきて。
今はエスパシンで色んなアクティビティをやって帰ってくるから、お風呂に入ってすぐに寝てしまいます。今日は何をしたのか、嬉しそうに話してくれます。
――娘さんをブラジル学校に入れたのはブラジルに戻ることを念頭に入れてのことですか?
いいえ、本当は日本の学校へ入れようと思ったんだけど時間帯が…。ブラジル学校だったら(親の仕事に)時間を合わせてくれるから。

エスパシンは子どもたちに向き合うだけでなく、かれらの親たちを取り巻く環境やニーズにも細かく対応している。
その背景には、日本社会の中でブラジルルーツの人々が置かれた位置があるだろう。不安定な労働や生活は昔からあまり変わっていない。
大人たちの中には、工場と自宅を行き来する毎日に追われ、それ以外の人間関係やコミュニティにつながっていない人も多い。日本語を体系的に学べる機会も少ない。そんな親たちの居場所としても、エスパシンはある。
例えば、息子がエスパシンに通うヒカルド・プリモさんは、自動車部品の工場での仕事のかたわら、エスパシンでは大学時代に学んだ演劇の講師としても活躍している。若い頃はブラジルで子ども向けに演劇のワークショップをしていた経験もあり、それを生かしている。

今年のゴールデンウィークには大きな晴れ舞台があった。ブラジル児童文学の巨匠モンテイロ・ロバートのひ孫が講演会で来日する際に、エスパシンの子どもたちが練習してきた演劇を発表する機会を得たのだ。プリモさんは大張り切りだった。
シズカさんは言う。「彼にとってすごく良かったと思う。20数年ずっと工場で働いて、娘たちを育てあげて、でも彼自身は自己実現ができていなかったと思うから」
プリモさんは、これまで様々な工場や現場仕事の中で身につけたという日本語でこう語った。
「ここに来ると元気になる。体は疲れるけど気持ちが元気になる。だからできるだけ手伝いに来る。夏休みと春休み、できるだけ来る」

セウミーニャの愛称でみんなに愛されるセウマさんも、エスパシンを支える大人たちの一人。早朝や夜遅くに掃除をするのが彼女の役割だ。「シズカはもっとサポートが必要なの、だからインタビューも引き受けた」と話をしてくれた。
ブラジルでの生活の厳しさが増し、セウマさんが家族と一緒に再来日した2007年、息子は10歳で娘は4歳だったという。今では二人とも高校を卒業して大人になっているが、それぞれに課題も抱えながら日本で生きている。
彼女は自らの経験を通して子ども時代の大切さを痛感し、今ここにいる子どもたちのために活動するシズカさんを応援しているのだという。
みんなでお菓子をつくった理由
エスパシンではみんなでよく料理のアクティビティをする。
この日はキッチンに何人かの子どもたちが集まって「ブリガデイロ」というチョコレートのお菓子をつくり始めた。コンデンスミルク、バター、ココアを混ぜて鍋で加熱し、少し冷まして小さく丸めていく。最後にチョコスプレーをまぶせば完成だ。


彼女たちがブリガデイロを作っていたのには理由があった。
自分たちで食べるためではない。エスパシンに関わりのある大人たちに1パック500円で販売するためだ。
そこで得たお金は、カチアという女の子のために使う。みんなで行く水族館の遠足に、家庭の事情でお金が出せないからだ。
「(仲間が)遠足に行けなくなってしまったら、彼女たちが自分たちで解決法を見出しました」とシズカさんは経緯を教えてくれた。

カチアは日本語が全くわからない状態で8歳の頃に来日した。5年ほど前のことだ。
地域の小学校に入ったものの、十分なサポートがなく、授業の内容がほぼ理解できない状態が続いていたという。
放課後にエスパシンにも通い始めたのはそんな頃だった。彼女のこれまでを振り返って、シズカさんは言う。
「すごくもったいなかった。ポルトガル語も日本語もよくわからない、何にもわからないみたいになってしまって。ポルトガル語は忘れ始めていたんですね」
「彼女は今でこそ文章を読んで理解して、(色々なアクティビティにも)参加するようになったけど、最初の頃は何を読んでも、こちらが問いかけても『ん?』って感じで全然理解していなかった。彼女は日本の小学校に通ったんですが、授業で何も理解しないまま、ただ聞いているだけだったようです」

日本の中学校に進んだ直後、カチアは不登校になった。シズカさんは彼女の話に耳を傾けたが、自分の言葉を失っているようだったという。
「中学生になった途端に、毎日頭が痛いとか、そういうことが起き始めて。彼女はいつも明るくて元気な子どもだったのに、とても落ち込んじゃって」
学校を離れた子はカチアだけではない。かれらをこのまま放っておけないと考えたシズカさんは、日本での中卒認定や高卒認定の試験、あるいはアメリカの通信制学校など、様々な選択肢があることを示そうとしている。
「この子たちに、自分次第で希望する道に行ける、(ブラジルだって、アメリカだって、日本だって)どこへだって行ける、可能性はあるということを示すのが自分の役目だと思っています」

学校でのこと、家庭でのこと、これまで日本で様々な葛藤を経験してきたカチアにとって、エスパシンで過ごす時間にはどんな意味があったのだろう。
私たちが大垣を訪れてから何ヶ月か経ったあと、カチアが自撮りの動画に気持ちを語り、それを送ってくれた。
「誰かに叩かれたりいやなことをされたとき、前の私は何もできなかった。黙り込んでいた。それか泣いていたの。学校で男子からすごい叩かれたときに… 私は何もできなかった。やり返したくなかったし、やり返せば私が怒られて、私が悪いってことになると思ったから」

「だけど今は…。今度はここで別の子がちょっかいを出してきて、私は立ち上がったの。彼は私が言い返した迫力にびっくりして怖がったほどで、言い返すこともできなかった。そういうところが(私は)変わったと思う。友人関係も変わった。そんな感じ」
自分を否定する社会や他者に対して、自分の思いをしっかり言葉にする。彼女の存在を肯定する大人たち、一緒に楽しみ、互いに助け合える仲間たちとの時間を通じて、そんな強さを彼女は得たのかもしれない。
取材後記
エスパシンの毎日はシズカさんを中心としつつ、色々な大人たちの仕事やサポートによって成立している。
数名のコアスタッフに加え、多種多様な講座(語学、文化、スポーツなど)の先生たちがいて、日々の雑務を手伝ってくれる親たちもいる。

日系ルーツの夫と共に来日したリアンドラさんは、2020年に大垣でエスパシンに出会った。コミュニティメディアでエスパシンの記事を見つけ、面白そうだと直感して見学に訪れた。シズカさんともすぐに意気投合した。
世界のどこでも移民が直面する問題は似ているとリアンドラさんは言う。かつて自らが移民として生活したフランスでは、「何でここにいるの」、「国へ帰れ」といった言葉を聞いたり、面と向かって自分自身が言われたりすることも日常茶飯事だった。
エスパシンの子どもたちがこの社会で抱える困難に対処し、乗り越える方法を、どうあの子たちに教えられるか…。かれらに初めて出会った日、家に帰ってからもそのことが頭の中でぐるぐると回って忘れられなかったそうだ。

エスパシンはSNSやコミュニティメディアなどで積極的に発信している。いつも楽しい雰囲気で、明るいエネルギーに満ちている。
だが、その背景には子どもたちにも、親たちにも、それぞれの葛藤がある。今回の取材で改めてよくわかった。だからこそ、みんなで乗り越えようとしているのだと思う。
シズカさんたちが発信する日々の様子をスマホで眺めながら、私自身とルーツも年齢も近い彼女の取り組みがずっと気になっていた。
そして、ポルトガル語での発信が基本だからこそ、日本語でも彼女たちの存在やその前向きなチャレンジを伝えたいとも思った。その結果、この記事ができた。
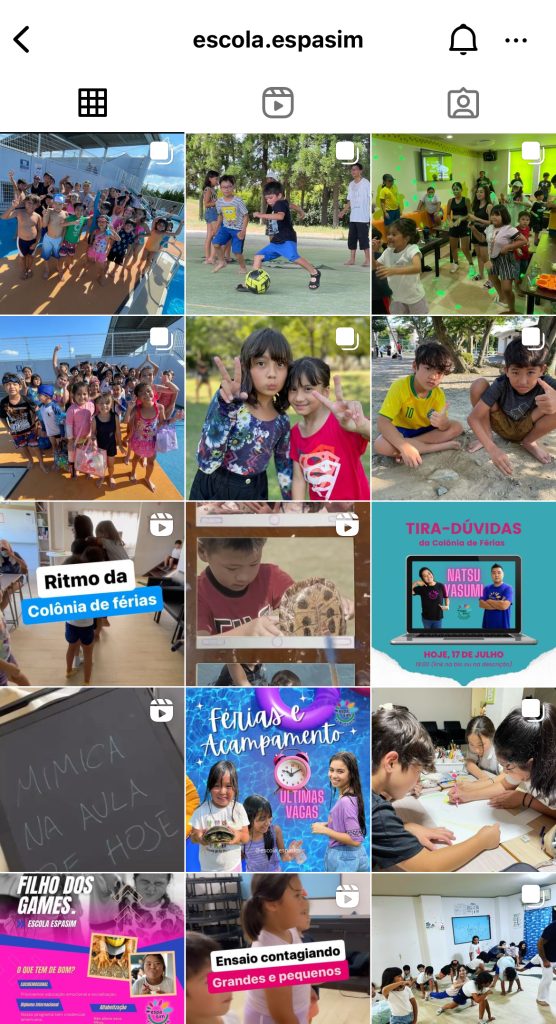
日本の学校で居場所を失う子どもたちがいる。ブラジル学校でも居場所を見つけられない子どもたちがいる。そんな「日本育ち」の子どもたちを、エスパシンはなんとか支えている。子どもたち同士も、助け合っている。
だが、かれらの努力に頼っているばかりで良いとは思えない。例えば今でも外国籍の子どもは就学義務の対象外で、日本国籍の子どもと異なり、自治体や学校から不就学のままに放置されている場合も少なくない(文科省の最新の調査によると、6〜15歳の外国籍の子どものうち、不就学か就学状況不明の割合が1割弱にのぼるという)。
また、エスパシンのように公的支援がゼロだったり、多くのブラジル学校のように不十分である場合、その費用はすべて親たちが負担せざるを得ない。シズカさんたちもやはり、ギリギリで運営している。
子どもたちに「日本人と同じようにしないとダメ」だと感じさせ、家族の出自(roots)や自分の生きてきた道のり(routes)を否定させるような状況も、変える必要がある。
ミヤワキ・シズカさんの挑戦、エスパシンに集う子どもや大人たちの挑戦をたどってきた。そこで見えてきた様々な課題や困難は、この日本社会のあり方として、私たち自身が向き合っていくべき現実であるはずだ。

CREDIT:宮ヶ迫ナンシー理沙(取材・執筆)、柴田大輔(取材・写真)、望月優大(取材・編集)
*この記事には同内容のポルトガル語版もあります(ニッポン複雑紀行で初の二言語記事の試みです)/ Segue o link do artigo em português. > 20 anos no Japão. O desafio de Shizuka Miyawaki que se acompanha as crianças que “crescem no Japão”
「ニッポン複雑紀行」の活動は毎回の記事を読んでくださる皆さま、そして難民支援協会への寄付によって支えられています。SNSなどで記事を広めてくださることも大きな励みになります。これからも関心をお寄せください。


