
2018.11.01
「日本の父」に会いたいと願う子どもたち。「フィリピンの母」の苦悩と誇り
「フィリピンパブ」の歴史
日本から飛行機で4~5時間の距離にあるフィリピン。この国と日本の歴史は長い。
豊臣秀吉の時代には両国の間で交易が行われ、江戸時代にはマニラに日本人町が形成されていたといわれる。明治時代から戦前にかけて、日本政府の主導で日本人移民が入植し、マニラ麻の栽培に従事した。戦時中は日本軍がフィリピンを占領し、甚大な被害をもたらした。

そして戦後、外国人労働者の受け入れを公に認めてこなかった日本が事実上いち早く門戸を開けたのは「エンターテイナー」とよばれるフィリピン人女性たちに対してだった。
高度経済成長を遂げた日本は1980年代、歓楽街での人手不足から、フィリピン人の女性たちに対して「興行ビザ」の発給を始めた。興行ビザは芸能やスポーツなどのために来日する人に与えられるビザだ。
女性たちはフィリピンでオーディションに合格し、歌やダンスのレッスンを経て日本にやってきた。しかし、実際の彼女たちの仕事の中心は客の接待であり、同伴(店外デート)や売春を強要する店もあった。
こうした矛盾を抱えながらフィリピン人女性たちが働く店は日本全国に拡大、いわゆる「フィリピンパブ」として定着していく。当時は年間数万人のフィリピン人女性が日本へと入国した。

しかし、各地で女性たちが暴行や性的虐待を受けていたことなどが明るみになり、日本への国際的な批判が徐々に高まっていく。2005年からは興行ビザ発給の条件が厳格化され、その後興行ビザによる入国は減少した。
20年以上続いた大規模なエンターテイナーの受け入れは多くのフィリピン人女性たちの人生を左右した。日本人男性と結婚した女性もいれば、客との間にできた子どもを未婚のまま出産した女性もいる。
こうした背景から、1980年代以降、日本人とフィリピン人の両親から生まれる子ども「ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン(略称 JFC)」の出生が増え、現在その子どもたちの数は日本フィリピン両国を合わせて数十万人にのぼるともいわれている。
現在、マニラ首都圏で暮らすローズさんもかつてエンターテイナーとして日本に渡った一人だ。彼女には客だった日本人男性との間に生まれた現在20代の子どもが二人いる。彼女はこれまでどのような人生を歩んできたのか。ローズさんの家を訪ね、息子のヒロさんと一緒にお話を聞いた。

(*本文中の母子の名前は、ニックネームで表記。)
エンターテイナーから日本人との子どもを持つシングルマザーに
――ローズさんが日本へ行くことになった経緯を教えていただけますか?
ローズ:ハイスクール卒業後の17歳のとき、付き合っていた男性との間に子どもができて出産しました(※当時のフィリピンのハイスクールは中学と高校を合わせて四年制だったため16歳で卒業)。
フィリピンでは仕事の機会が少なく給料も安いため、シングルマザーとなった私は、母に娘を預けて日本に行くことにしたんです。私はダンスが好きでしたし、その頃は日本行きをあっせんするエージェントがたくさんありました。

――日本に行くのは怖くありませんでしたか?
ローズ:フィリピンでは国内に仕事が無いので、海外へ働きに行く人も多いです。私も海外への憧れがあり、怖いというより冒険に行くような感じでした。合計四回日本に行き、広島、松山、東京で働きました。
最初に日本に来たときは毎晩泣いて過ごしていました。当時はインターネットもなかったので、フィリピンとは月一回の手紙でのやりとりだけでした。店によってはオーナーがヤクザというところもあったようですが、私の働く店のオーナーは運良くいつもいい人でした。

最初の店は同伴も禁止していましたが、その代わり手に入るお金は月300ドルだけでした。住む場所と食事は提供されていたので、月給の二割くらいをフィリピンに送金していました。
四回目に日本に行ったとき、お客さんだったヒロの父親と出会って結婚したんです。ホテルのチャペルで結婚式も挙げました。
――日本での結婚生活が始まってみてどうでしたか?
ローズ:当初はうまくいっていました。夫は最初、長女を日本に呼びせることにも賛成してくれました。夫の両親も親切にしてくれ、日本料理も教えてもらいました。「けんちん汁」とかですね。
けれど二年ほどたった頃、彼は私がパブの仕事を続けていたことを気に入らず、けんかをするようになったんです。フィリピンでは結婚しても女性が働くことは当たり前ですし、フィリピンにいる娘と母に少しでも仕送りしたいとも思っていました。でも彼はそれを理解できませんでした。

――文化の違いがあって難しかったということでしょうか?
ローズ:そうですね。それに私はまだ23歳でしたから考えが幼いところもあったと思います。夫は私と彼の娘でもある次女に暴力をふるうようにもなりました。
長男のヒロを出産したときはとても喜んでくれたのですが暴力はやみませんでした。ヒロが一歳になる頃、彼の暴力に耐えかねてフィリピン大使館に助けを求めたんです。それから修道会のシェルターにかくまってもらい、支援を受けてフィリピンへと帰国しました。
フィリピンに帰国してからは、私の精神的な落ち込みがひどく、アルコールにおぼれる生活になりました。仕事もできず私の母がレストランで働いて家計を支えてくれたんです。電気も水道もない、木切れでつくった家で暮らしていました。子どもたちは外で「ジャパゆきの子ども!」といじめられて帰ってきましたが、そのときは自分自身のことで精いっぱいでした。
子どもが学校に行くようになってから、手紙で夫とやりとりをし、毎月一万円程度は養育費を送ってくれるようになりました。私もなんとかどん底の状態から這い上がり、洗濯婦などの仕事をして家計を支えました。けれどもヒロが高校生のときに送金も連絡も途切れてしまい、ヒロは働きながら高校を卒業することになります。

――ヒロさんはお父さんのことを何か覚えていますか?
ヒロ:日本にいた頃のことは小さすぎて何も覚えていません。私がフィリピンに帰ってからも父はクリスマスにプレゼントを贈ってくれました。電話もしましたが、互いの言葉がわからなかったので「元気ですか?」という程度の会話でした。
以前は日本の写真もたくさんあったのですが、昔の家に住んでいたときに洪水があってほとんどダメになってしまいました。お母さんからは、お父さんが地方の農村から上京してエンジニアになりその後は一流の企業に務めている素晴らしい人だと聞いてきました。
――お父さんがいなくてどんなことが辛かったですか?
ヒロ:「お父さんはどうしているの?」と友達に聞かれても答えられないのが辛かったです。「父の日」も嫌いでした。女性ばかりの家庭で育ったので、思春期の頃は男性らしい物事のとらえ方や行動がわからず、戸惑いました。母は知人の男性に聞いたことを教えてくれたり、参考になりそうな本を買ってきたりして、父親の穴を埋めようとしてくれました。
経済的な面では、お父さんの支えがなくなってから、教科書や体育着を買えなかったり学校行事に参加できなかったりしたのが辛かったです。

――今お父さんに対してどんな気持ちを持っていますか?
ヒロ:幼いときは父を慕う気持ちしかありませんでしたが、成長するにつれてだんだんと不信感、憎しみなどいろいろな感情が湧いてきました。
でも母はそんな僕に対して、離れて暮らしてコミュニケーションも難しい中で父親が長い間生活を支えてきてくれたことを話し、それはきっと私たちを愛してくれていたからだろうと言いました。今はお父さんの気持ちもわかるような気がします。

――ヒロさんのラストネームはお父さんの姓ですね。日本人の姓名を持っていることについてどう思いますか?
ヒロ:フィリピンでは私と同じ名前の人はおそらくほかにいないでしょう。フィリピンで唯一の名前を私は誇りに思います。日本は自分が生まれた国ですしいつか帰りたいです。
経済的な理由で大学を中退しましたが、今はコールセンターで働きながら大学の社会人コースで勉強しています。日本で仕事を見つけるためにも大学を卒業したいです。得意な英語を生かして日本で英語教師として働ければと思っています。
――日本に行けたらお父さんにも会ってみたいですか?
ヒロ:はい。今お父さんは60歳になっているはずです。もしお父さんに会えたとしてももう何かを求めることはありません。ただ私たちのこれまでのことを話して26年間の空白を埋めたい。それにお父さんはもう若くないので私が世話をしてあげたいです。

父を失った母子に寄り添ってきた日本人たちの存在
ローズさんは日本で結婚し日本で子どもを出産したが、エンターテイナーだった女性のなかには日本で子どもを妊娠した後フィリピンに帰ってから出産した人も多い。興行ビザの在留期限は最大でも六ヶ月だったため、出産前に帰国する必要があったのだ。日本行きをあっせんしたエージェントも、彼女たちが契約中に日本人と結婚することを禁止したり、妊娠したらフィリピンに送還するということを約束させたりしていた。
そんな事情を見越していたのか、すでに家庭がありながらもそれを隠してフィリピン人女性と交際していた日本人男性も少なくない。子どもが生まれたばかりのころは父親がフィリピンに会いに来たり、養育費やプレゼントを贈ったりしていたものの、いつしか連絡が途絶えて母子が取り残される。そんなケースが1990年頃から目立つようになった。


こうしたなか1994年に日本の弁護士と市民によるNGO「JFCネットワーク」が立ち上がり、父親探しや認知、養育費の請求などの法的支援を開始。2009年以降は子どもの日本国籍取得も支援してきた(※09年に国籍法が改正され、日本人の父親から認知を得た子どもは20歳以前に届出をすれば日本国籍取得が可能になった)。
母親が日本人であれば、こうした子どもの権利を求めて自ら手続きをとることもできるだろう。しかし、日本の法律を知らないフィリピンの母親たちにはその術がなく、そのなかでJFCネットワークが果たしてきた役割は大きい。
JFCネットワークのフィリピン事務所「マリガヤハウス」(マリガヤはタガログ語で「幸せ」の意味)は、フィリピンにいる母子からの相談窓口になっている。先述のローズさんもそうだったが、母親たちの多くは子どもの前で父親のことをあまり悪く言わないという。
ディレクターの河野尚子さんは次のように語る。


「お母さんたちは『子どもに親を憎んで大人になってほしくない』と言います。けれど(子どもが父親からの)認知を得るために裁判を起こさなくてはならないような場面でも『それはかわいそう』と躊躇する人もいて、複雑な気持ちになります。何だかお母さんが自分のことを卑下しているように感じるんです」
河野さんは続ける。
「父親がいないことで、お母さんは子どもに対しても引け目を感じています。そのために子どもに対してあまり厳しく叱れなかったり、父親に対して過度に期待を抱かせてしまったりすることもあります。でも実際には父親が認知しないこともよくありますし、たくさんの困難が待っているんです。お母さんたちにはそれを子どもにきちんと伝えたうえで『それでも前に進んでいかなきゃいけないよ』と示してほしい。そういう強さが必要なんです」
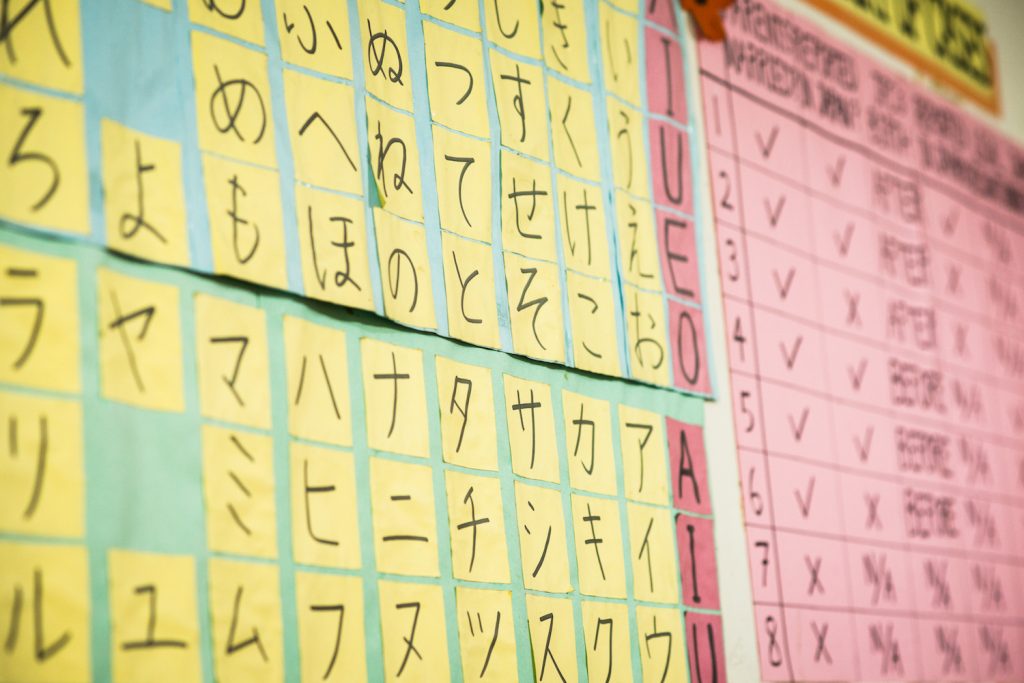
父親の国を目指すJFCたちを待ち受けているもの
新宿にあるJFCネットワークの東京事務所には、フィリピンから日本に来たJFCの青年たちがたびたび顔を出す。大人になり、自ら父親に会いに日本に来たのだ。JFCネットワーク事務局長の伊藤里枝子さんにお話を聞いた。
――父親に会えるケースは多いのですか?
せっかく日本に来ても実際に父親と再会できて歓迎される子は少ないです。JFCネットワークが支援してきた子の中には、日本に来る前に父親の認知を得た子もいます。でも、そのなかには父が自らの意志で認知をするのを嫌がったために、裁判を起こして認知を得た子どもたちもいます。
法律上は認知されても父の心では“認められていない”子も多いのです。そのため、父の家まで訪ねて行ったのに門前払いをされてしまった子もいます。

――日本で生活していくことも簡単ではありませんよね?
いろいろな相談が寄せられますが、労働に関する相談は多いですね。かれらは知人のツテを頼ったり技能実習制度を利用したり、エージェントを通じたりして来日します。そのなかには私たちが支援して日本国籍を取ったJFCも多いのですが、日本語がほとんどできないために低賃金で働いていたり、知らないうちに多額の借金を負わされていたりする子もいます。
日本国籍のあるJFCたちは日本への渡航や就労の制限がないことからエージェントにとっては利用しやすく、また日本語があまりできないことから騙しやすいため、安価な労働力として利用されがちです。マリガヤハウスでワークショップを開くなどして、その危険性を伝え啓発活動もしていますが、日本をめざすJFCは後を絶ちません。かれらが日本をめざす大きな理由は、働けて稼げる国である以上に「父の国・日本」だからなのです。
――せっかく日本国籍を取得したのに、悪質なエージェントに利用されてしまう…。支援者として歯がゆいところかと思いますが?
そうですね。日本国籍を取得したからといって、それがすぐに彼らの幸せに結びつくわけではないです。でも、「日本国籍取得」が一人ひとりの人生の選択肢を増やしたことは確かですし、彼らがその後、何を選びどのような人生を歩んでいくのかを決めるのは本人次第です。
日本国籍取得後に来日して、さまざまな苦悩やつらい経験があっても、かれら自身が自らの経験で「日本」を学び「日本人」を経験するなかで、一人の「JFC」としてアイデンティティを形成し自尊心を養っていってほしいです。

――日本の社会に対して、これからどのようになってほしいと思いますか?
すでに日本には多様なルーツを持つ人が暮らしていて、「日本人ってこうだ」という型にはめるのは不可能になっています。にもかかわらず、相変わらずステレオタイプ的な「日本人像」に固執する傾向がまだまだ根強く残っています。
JFCをはじめ多様なルーツをもつ当事者たちが隠れるのではなく、声を上げ、行動をしていくことが、日本社会に多様性を認めさせる大きな力となるはずです。その過程でさまざまな軋轢や衝突があるかもしれませんが、最終的に“多様性”はストレスレスで心地よいのだ、と考えられる社会になってほしいし、そうしたいですよね。
団結する母親たち それぞれの誇り
今年の夏、マリガヤハウスではJFCの母親たちの自助グループ「TINKABA(Maligaya House Tinig at Karapatan ng Kababaihan の略称)」が立ち上がった。 このグループ名には「女性の権利をさけぶ」と言う意味がこめられている。活動はまだ始まったばかりだが母親同士が交流を深め、協力しあい、エンパワーしていくことを目指している。

グループ活動の日にお邪魔すると、はつらつとした様子で昼食づくりや話し合いに参加するお母さんたちの姿があった。グループセッションの時間を借りて、こんな質問をした。
――みなさんはご自分について何か誇りに思うことはありますか?
ミカイさん:家族を支えるために大学を中退して日本に働きに行ったとき、「教師だった親の頭の良さを引き継いでいない」と周りから言われて悔しい思いをしました。でも帰国後は、マニラの大手生命保険会社に採用されて働くこともできましたし、積極的に新しい仕事に挑戦してきました。外に出て人と会い、自分を成長させる努力をしています。

エミさん:子どもの父親と連絡がつかなくなったとき、私の気持ちはぐちゃぐちゃでしたが、兄弟の助けを借り、コンピューターショップを開いて何とか子どもを育ててきました。子どもが自立したとき苦労しないように、洗濯のしかた、食事のつくり方もすべて教え、今はどこに出しても恥ずかしくない大人に成長しました。今ようやく「本物の母親」になれた気がして、そのことが誇りです。
ミドリさん:働いたお金で兄弟を学校に通わせ、昼食代やおこづかいまですべて面倒を見てきました。息子についてもきちんと学資保険を積み立てておいたことで、大学まで出すことができました。だから今、息子には「父親に受け入れられなくても自分の道を進んでいけばいい」と伝えることができます。
最後にミドリさんは力強くこぶしを掲げた。「ファイトー!」

取材後記
フィリピンパブ全盛期の1990年代、エンターテイナーとして働くフィリピン人女性はドラマや映画の題材になり、幅広くその存在が知られるようになった。しかし、そのなかには女性たちを「金のためならなんでもするふしだらな女」として描いたものも目立った。
90年代に活躍した女優ルビー・モレノ。自身もフィリピン出身のエンターテイナーとして働いた経験をもつ彼女は、日本の映画やドラマで自分に与えられた役柄について後にこう記している。
「実際に日本に働きに来ているフィリピン人女性の平均像というわけでなく、どこかクセのあるキャラクターが大半だった。それはドラマや映画を制作する人たちが、ジャパゆきさんに対して持っているイメージに由来するものであった」
当時、多くの日本人はメディアが映すイメージを通じて彼女たちの存在を認識しただろう。私自身も学生時代に地元駅前の店に出入りする女性たちを偏見の目で見ていたことを覚えている。しかし、のちにフィリピンを訪れた私をローズさんもほかの母親たちも屈託のない笑顔で迎えてくれた。
フィリピンでは海外で働き祖国に送金する労働者は「国民の英雄」ともいわれる。彼女たちは家族、親族を養うために海を渡った勇敢な英雄であり、そこに確かなプライドを持っていることが感じられた。そして日本人の血を引く子どもを愛情深く育てる母親でもある。

女性たちの来日から30年ほどの月日が経ち、今はその子どもたちが父親を求め、また日本人としてのアイデンティティを確かめるために日本に来ている。だが、30年が経った今もなお、母親たちの時代と同じように、かれら子世代が安価な労働力として日本社会で利用されている現実があることには日本人として恥ずかしい思いがする。
同時に、多くのJFCたちが日本の言葉、文化、慣習を吸収しながら、前を向いて生きていることも最後につけ加えておきたい。日本で働くとあるJFCの女性はこう話す。
「日本人の長所は規律正しいところでフィリピン人の長所はファイティングスピリットがあるところ。私はジャパニーズ・フィリピノ・チルドレンとして、その両方を大切にしたいんです」
来日して三年目の彼女は、工場の従業員を経て、今は英語教師として働いている。現在は後輩の指導にもあたり、日本の英語教育を支えるフィリピン人をたくさん育てたいと意気込む。
私はJFCたちがもつフィリピン仕込みのファイティングスピリット、そしてそれぞれの人となりに日本でもっともっと触れたい。そして、もっとたくさんの人にかれらのことを知ってほしいと思う。
きっとそこから、新しいパワーが生まれてくるはずだ。

参考文献
・「フィリピン女性 エンターテイナーの世界」マリア・ロザリオ・ピケロ・バレスカス著 津田守監訳 小森恵・宮脇摂・高畑幸訳(明石書店)
・「フィリピン―日本国際結婚 移住と多文化共生」佐竹眞明 メアリー・アンジェリン・ダアノイ著(めこん)
・「日本のお父さんに会いたい-日比混血児はいま-」松井やより編(岩波書店)
・「悲しい国、ニッポン」ルビー・モレノ著(立風書房)
CREDIT
野口和恵|取材・執筆
柴田大輔|取材・写真
望月優大|取材・編集
関連記事
・二つの祖国をもつ親子。母と息子、それぞれにとっての「帰る場所」とは?|野津美由紀
・「日本人」とは何か?「ハーフ」たちの目に映る日本社会と人種差別の実際|下地ローレンス吉孝
ーーーーー
野口和恵さんの著書『日本とフィリピンを生きる子どもたち――ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン』(あけび書房)もぜひ合わせてお読みください(編集部)。


