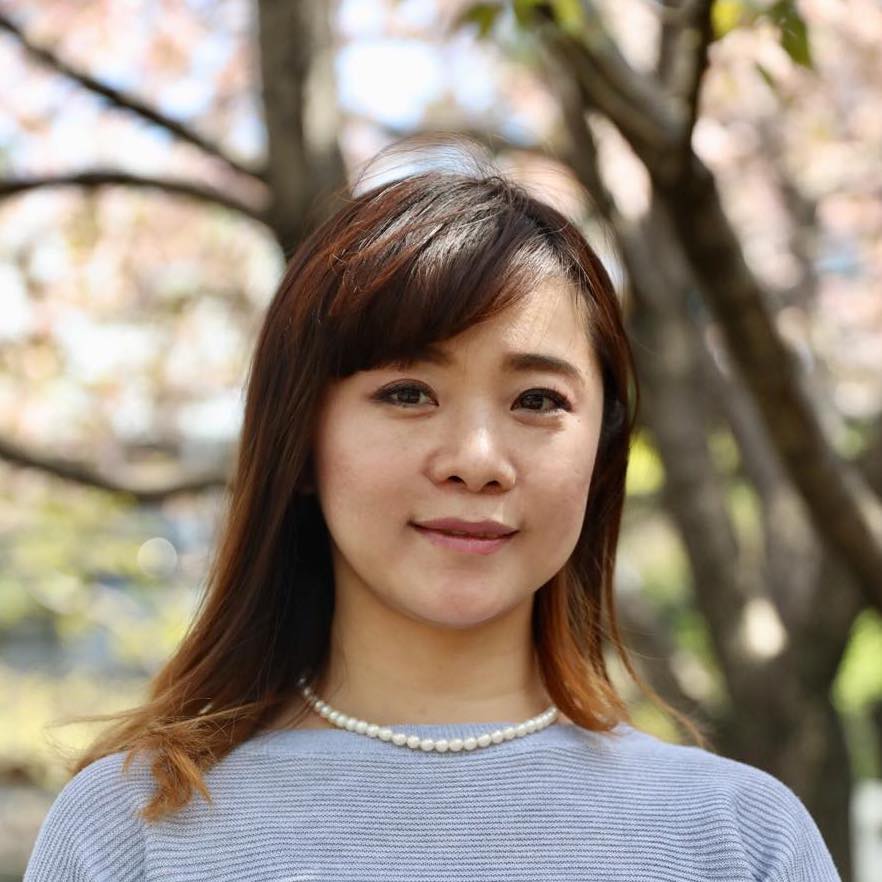2018.04.19
病院で通訳する子どもたち。ペルーから来た11歳の少年が「プロの医療通訳」を広める伝道師になるまで
「医療通訳」という問題系
はじめまして。二見茜と申します。普段は医療現場にて外国人医療の研究に従事しています。海外にルーツのある方たちが安心して医療機会にアクセスできる社会になるよう、諸外国の取り組みなどにも学びながら日々の研究を進めています。

早速ですが、皆さんは「医療通訳」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
日本で暮らす多くの外国人にとって最も大きな障壁の一つになるのが病院での言葉の問題です。病院で交わされる情報は専門的であったり、痛みの表現などとても繊細なものであったりします。しかし、ごく限られた一部の病院を除いて、日本では患者側が通訳を一緒に連れてくるというのが一般的な対応となっています。病院側ではなく、患者側が言葉の問題を解決するのが常識になっているということです。
しかし、英語はともかくとして、その他の様々な外国語と日本語の通訳が日本中にいるわけではありません。しかも、仮に近くに母語を解する通訳の方がいたとしても、もちろんそのサービスが無料で利用できるわけでもありません。ニッチな言語であればあるほど、金銭的な意味も含めて市場にある通訳サービスの利用は難しくなります。

では、日本語に不自由のある外国人はどうしているか。家族や同じルーツのコミュニティの中で、母語と日本語の両方を使える人たちがボランティアの通訳として活躍しています。活躍することを余儀なくされている、と言ったほうがより正確かもしれません。
重要なことに、こうしたボランティアの通訳の多くは「子どもたち」によって担われています。なぜなら、単純に子どもたちの方が日本語を学ぶスピードが早いからです。例えば、親たちが黙々と工場のラインで働いている間に、子どもたちは日本の小学校で学んでいる、そんなケースを想像してみてください。親子の間で日本語習得のスピードに差が出てくるのは当然のことです。
私の知人にカブレホス・セサルさんという日系ペルー人の方がいます。1990年に11歳でペルーから来日し、長年に渡って家族や日系ペルー人や日系ブラジル人のコミュニティのために医療通訳の役割を担ってこられた方です。

セサルさんは現在「多言語医療通訳のコールセンター」を提供する会社で働いています。私が彼と知り合ったのも、私が勤める病院でその会社のサービスを導入したことがきっかけでした。
セサルさんは幼少期に始まった通訳のボランティアから、コールセンターという仕組みでの対応に至るまで、この国の医療通訳の実状を幅広く知っているとても貴重な方だと思います。今日は彼の長年にわたる経験を伺うなかで、医療と言葉、病院と外国人という文脈で、この社会が抱える課題や解決の方向性について考えることができたらと思います。
ハイパーインフレとテロを逃れ、バブル期で労働力が不足する日本へ
――セサルさん、今日はよろしくお願いします。まずはセサルさんのご家族について教えていただけますか?
よろしくお願いします。私は日系ペルー人で、私のひいおじいさんとひいおばあさんが熊本からペルーに移住しています。その娘のおばあさんがペルー生まれで日本国籍を持っていて、彼女がペルー人と結婚して4人の子どもをつくりました。その長女が私の母親です。私は二人兄弟で弟がいます。
――セサルさんの3世代前に日本からペルーに移住しているんですね。セサルさんが日本に来たのはいつ頃ですか?
私が家族と日本に来たのは1990年で11歳のときですね。泣きました…。それまでの友達と別れるのがすごく悲しかったです。
きっかけになったのは治安と経済です。80年代後半から90年代初頭のペルーは治安が非常に悪くて、武装組織によるテロ事件も頻繁にありました。経済はインフレで、例えば、以前は高級車が買えたようなお金でマッチ箱1箱しか買えなくなってしまう、そんな状況でした。その影響で、祖父の会社も倒産してしまいました。

――ハイパーインフレですね…。
私の父は農薬の会社で営業の仕事をしていました。彼はペルーとコロンビアの国境にあるアマゾン地域を担当していたのですが、1989年のある日にテロリストに拘束されてしまったんです。1日ほど木に縛られて頭に布を被されていたそうなのですが、なんとか無事に釈放されたそうです。でも、彼らに農薬の売上金を取られてしまって、会社からもそのとき失ったお金を給料から天引きされる羽目になってしまい、「この国で働き続けるのは危ない」と思うようになった。
――すごい経験…。
ペルーでは1990年に日系人のフジモリさんが大統領になりました。そして、ちょうどその頃日本でも法改正があって。日本は当時バブルで景気がよかったので、労働力として日系人を受け入れることになりました。
そういった経緯もあって、ペルーにあった家などをすべて売って、家族や親戚20人全員で日本に来ることになったんです。
――ペルーでの生活の悪化とバブル期の日本が日系人を労働力として求める構造が合致した時期だったわけですね。
はい、ブローカーから派遣された仕事場によって親戚が3つの街に分かれました。横浜の自動車工場、埼玉県朝霞市の弁当工場、静岡県富士市の製紙工場です。私と私の両親は朝霞でした。
弟の交通事故、初めての通訳
――セサルさんが日本に来たときには日本語はどれくらいできたんですか?
ペルーで私立の日系の小学校に行っていたのですがほんの少ししかできませんでした。挨拶程度ですね。日本の小学生が英語を覚えるのと同じくらいなんです。ABCを覚えてPPAPが分かるくらいなんですよ(笑)。ペルーで小6は終えていたのですが、日本ではもう一回小6に入ることになりました。でも、両親はほとんど日本語ができなかったので家族の中では私が一番日本語を覚えていました。
――そうだったんですね。
日本に来て半年くらい経った頃に、当時3歳くらいの弟が道路に飛び出して車に轢かれてしまいました。その時に初めての通訳をしました。

家族の中で一番日本語ができた、とは言ってももちろん片言ですよ。それでもお母さんと救急車の人との間の通訳、病院の医師や看護師との通訳、警察との通訳、両親の会社の人との電話での通訳、それと事故の相手の保険会社との通訳。全部やりました。
――12歳の頃ですよね…。
はい。当時は医療に関する知識も全然ありませんでした。先生から「弟さんの頭の中に血の塊が3つできています」と言われたのですが、でもその危険性が私にはちゃんとわかっていなくて。そうしたら先生が私がわかっていないことを理解して「これが破裂してしまったら弟さんは亡くなる可能性があります」と言ったんです。その時に初めて「あれ、これは危ないのかもしれない…」と思って両親に伝えました。
――お医者さんが言っていたことをそのまま伝えたということですか?
そうです。そのまま伝えました。私の言葉で「血の塊があって、これが破裂したら死ぬかもしれない」と。そして「手術ができないから、薬で塊がなくなるのを待つしかない」ということも伝えました。お母さんは「理解したくないから理解しない」というような感じでした。「ちゃんと(先生の言葉が)わかってるの?」とお母さんから聞かれて、先生にも何度か確認をしました。
――最初の通訳のきっかけが家族の事故だったんですね…。
子どもだったので言われたことを通訳するだけでした。医者から「こう言って」って言われたらその指示に従う。逆に両親からも「こう伝えて」っていう指示があるので、それに従う。言葉がわからない、語彙力が少ないから「なんとか伝えなきゃ」って自分の言葉で伝えようとしていたと思います。大人の会話の場に子どもを入れるっていうプレッシャーはあったと思いますね。
――「子どもに通訳をさせてはいけない」というのは医療通訳の一般的なルールとして言われていることですね。現実には守られないことも多いということだと思いますが…。
そうですね。乳がんの方に告知をしたこともありました。それが一番辛かったかな…。日系ブラジル人で母親の友達の友達でした。母親も直接は知らない人です。30代半ばくらいだったと思います。
もう転移していたので余命があと3ヶ月くらいということでした。たぶん多く見積もってということだったと思うのですが…。残される家族や子どもたちのことを考えてかわいそうだなと。自分の母親がもしこうなったら…ということも考えました。
「セサルだったら通訳できるよ」
――本当に責任が重い通訳をよくやっていましたね…。セサルさんはいつから家族以外の人たちのためにも通訳をするようになったのでしょうか?
はい、弟の事故がきっかけになって、家族だけでなく親戚の中で「セサルだったら通訳できるよ」という話が広まっていきました。12歳の私と3歳の弟の間には8人くらい従兄弟がいたのですが、私が一番年上でした。日本語ができない大人たちが頼ったのが子どもたちの中でも一番上の私だったというわけです。

――「一番大きい子ども」だったんですね。
そうなんです。例えば静岡の親戚から「入管に行きたいから一緒に来てほしい、交通費は払うから」と言われたり、「誰々が警察に捕まってしまったので、事情をきちんと説明できないから一緒に警察まで来てほしい」と言われたり。そんな形で親戚から通訳を頼まれたりするようになっていきました。
しかも、私がいた埼玉に比べて神奈川とか静岡ってペルー人のコミュニティが大きいんですよね。だから、そこで知り合いが増えると「日本語の通訳できるんだって?」とさらに頼まれるようになっていきました。それが高校生くらいまでずっと続きましたね。
――セサルさんのような子どもたちは学校での時間を通じて日本語が上達していったと思うのですが、大人たちはなかなか日本語ができるようにならないという感じでしたか?
そうですね。私が高校に入る頃に朝霞から静岡の富士市に移りました。両親が働いていた朝霞の弁当工場の時給が良くなかったので、より時給の高い静岡の製紙工場で働くことになったんです。
静岡は日系人のコミュニティが大きくて、特に浜松に初めて行ったときには「なんだここは!」とびっくりしました。日本語ができなくてもスペイン語ができればちゃんと生活できます。日系ブラジル人が多くて彼らはポルトガル語を話すのですが、ポルトガル語とスペイン語を混ぜた「ポルトニョール」という話し方を覚えていくことでお互い会話ができるんです。
みんな週6日は働くんですが、残りの1日をどう使うかというところで、ここでは日系人同士で一緒にバーベキューをしたりダンスをしたり、自分たちの文化を通すことができるんです。私の父親もそれで楽に感じることができたというのがあると思います。
――静岡に移って学校の様子も変わりましたか?
それまでの4年間は友達は日本人しかいなかったのですが、静岡の高校に入ったらベネズエラ出身の日系人がいたり、ペルーの日系人もいて、「ここはちょっと違うな」というのがわかりました。

それまでの人生のことで共感し合える人たちと話ができたのはとても嬉しかったです。中学時代の日本人の友達は、自分や家族の苦労を知らなかったので。
患者が通訳を連れてくるのが当たり前
――当時は静岡のような日系人のコミュニティが大きなところでも医療通訳の仕組みは整備されていなかったのでしょうか?
ないですね。病院では患者の側が誰かを通訳として連れてくるのが当たり前でしたから。コミュニティの中から誰か連れてきてっていうのが指示でしたね。
次の予約を取るときにも、「いつにしますか」というだけではなくて、「一緒に日本語わかる人を必ず連れてきてくださいね」と言われます。つまり、「通訳はあなた次第だからね」というスタンスなんですね。
――医療には難しい言葉もたくさんあると思うのですが、それについてはどうやって勉強していたんですか?
医学の教科書を読みながらしっかり勉強するようになったのは20代半ばくらいになってからです。静岡から東京に来るちょっと前ですね。
それまでは先生に「これって何ですか、わからないです」と聞きながら、電子辞書を使って言葉を探したりしていました。また、「英語で何て言うんですか」と先生に聞いて、英語で先生が回答すると、自分ではなくて患者が分かるということもありました。私だけで完全に通訳をしていたというよりも、患者と協力しながら通訳していたという方が正しいのかもしれません。
――なるほど。外国人の方が病院に行くときに、言葉の面で一番困ることってどんなところなんでしょうか?
どこがどのように痛いのか、そういったことがうまく伝えられないことです。例えば「しゃがんで数秒経つと頭が重くなることがある」ということが伝えたくても伝えられない。患者が、実際にしゃがんでみて、立ち上がって、と身振りで伝えようとしても、なかなか伝わらないんですね。
あとは、みんなが口を揃えて言うのが、「お医者さんが話すときに早すぎてわからない」と。
――聞き返したりはしづらいのでしょうか?
聞き返す人ももちろんいますよ。でも聞き返さない人も多いです。2回、3回と聞くと「迷惑をかけているかな」と気になってしまったり、中には変な顔をするお医者さんもいますから。
通訳を仕事に。そして再び医療通訳の世界へ
――今は医療通訳を広げる仕事をされていると思いますが、ボランティアではなく仕事として通訳に関わるようになった経緯を教えてください。
高校を卒業した後は静岡の専門学校でデザインを勉強していました。でも当時の夢はプロドライバーになることだったんです。富士スピードウェイで走りたかった。
23歳のときに子どもができました。そのときはゴムの工場でアルバイトをしていたのですが、私だけの給料でやっていけるのか、このままプロドライバーの夢を持ち続けていいのだろうか、と不安になったんです。

――持っていた夢に迷いが出てきたんですね。
はい、そのとき人生で初めて夢がなくなってしまったんですよ。もちろん良い父親になる、家族を養うっていうことはあったのですが、個人としての夢がなくなってしまった。それからの数年間は人生のスランプのような時期だったと思います。
27歳のときです。ある日、妻から「通訳としてお金を稼いでみない?」って言われたんです。フリーペーパーを渡してきて「通訳できる人を募集しているみたいよ」って。でも自分はそれまでずっとボランティアで通訳をやり続けてきたので、通訳を自分の職業にするとは全く思っていなかったんですね。だから「できるわけないでしょ」と思いましたし、東京に面接に行くための新幹線代もバカにならない。
すると妻が「会社に前借りしてでも行きなさい」と言うので、会社にお願いをして面接に行きました。そうして3回目の応募でようやくコールセンターでのスペイン語とポルトガル語の通訳の仕事で正社員の契約を得ることができたんです。
――その会社が今働かれているランゲージワン社ですか?
いえ、ワールドサポートという会社でした。2006年のことです。そこでは医療ではなく、ガス、携帯キャリア、保険、不動産、鉄道など様々な領域での通訳をやっていました。
その後にディーキュービックという会社に移って医療関係の通訳をやるようになったのですが、今勤めているランゲージワンという会社はディーキュービックの事業部が2015年に独立してできた会社なんです。
医療通訳を「仕事」にして見えてきた課題
――インタビューの終わりに、「ボランディア」から始めた医療通訳を「仕事」にされた今だからこそ見えてきた課題について教えてください。
はい。まずは「質の統一がない」ということがあります。
例えば、ある通訳会社さんでは留学生を通訳のアルバイトとして雇っています。日本語力が十分なレベルにまでいたっていない状態で医療通訳をさせているということなんです。先ほどの子どもが通訳をしているという話に似たようなところがあります。
――現場でもクレームを聞くことがありますね。質が良くないと。
ランゲージワンでは通訳をアルバイトではなく社員として育成することを目指しています。半年から1年くらいでアルバイトから正規の職員になってもらうという仕組みです。通訳の質を高めるためには必要な仕組みなのですが、留学生をアルバイトとして雇うのに比べてどうしてもコストが高くなってしまいます。

病院側としても通訳を使ったときに「このサービスの費用を誰が払うのか」という話になるんですね。だから多くの病院が医療通訳の仕組みを積極的に導入してくれていないという状況です。これが二つめの問題です。
病院の中には通訳を導入しつつ患者に費用の負担を求めるところもあります。費用負担に行政が関わる場合でも、実際に何が起きるかというと価格競争です。「安く出せば取れてしまう」という状態なんですね。するとまた質の話に戻ってしまいます。
――医療通訳の質を担保する教育や資格の仕組みを作る必要がありそうですね。
そうですね。私の会社では医学的な知識も含めて通訳としてのスキルを高めるための仕組みをつくっています。また、病院側に医療通訳の理解を広めるための動画やウェブサイトを作ったりもしています。
――実際にランゲージワンの医療通訳サービスが利用されている病院はどれくらいの数があるんですか?
今年度は東京都の福祉保健局による「医療機関向け救急通訳サービス」を受託・提供しています。都内にある1000以上の病院がランゲージワンのコールセンターを利用できるという仕組みです。
また、現在私たちのコールセンターでは最大13の言語に対応することができます。(編集部注:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、インドネシア語、ネパール語、フランス語)
ーー都内では多くの病院で利用可能なんですね。今後もっと医療通訳が利用可能な病院が広がっていくといいですね。
はい、今はまだまだ医療通訳へのニーズに対する供給が質・量ともに足りていない状況だと思います。だからこそ、これからも自分の経験を生かしながら、日本社会の中で医療通訳の必要性を広く知ってもらえるように頑張っていきたいですね。

――セサルさん、今日は貴重なお話を聞かせてくださりありがとうございました!
取材を振り返って
日系ペルー人として11歳で来日し、期せずして家族やコミュニティのために「通訳」としての役割を果たすようになったセサルさんのお話を伺いました。
現在日本には医療通訳に関する公的な資格がありません。いくつか民間の資格がありますが、英語や中国語などメジャーな言語に集中しており、ますます多国籍化する日本の現状に対応しきれているとは言えません。メジャーな言語に集中するのは講習や検定などビジネス上の理由も大きく、ビジネス的な論理だけではマイナーな言語まで広くカバーしていくことは難しいのではないかと思います。
結果として、日本ではセサルさんのような子どもたちが通訳をする事例も珍しくないという状況が今も続いています。当然、医療の知識や通訳のレベルにもばらつきが出てしまいます。セサルさんの話からもわかった通り、これが日本における医療通訳の現状です。
外国に目を向けてみると、医療通訳の公的な仕組みづくりに取り組んでいる国もあることに気づかされます。例えばカナダでは、医療、司法、教育の行政サービス等においてカナダの公用語を第一言語としない住民に通訳サービスを提供しています。カナダで通訳として働くためには、州の移民・市民権省公認のコミュニティ通訳士試験に合格し、通訳養成プログラムを修了し、さらに、医療・法律等の専門分野の教育プログラムを修了しなくてはなりません。
日本の医療現場を見ていると、海外にルーツのある患者さんたちは病気が進行して重症化してから受診することが多いことに気がつきます。「なぜもっと早く来なかったのですか?」と聞くと、「日本語が分からないから」、「医療費がいくらかかるのか分からないから」と、病院での言葉やお金の問題を心配して受診が遅れた理由を説明してくださいます。
医療は人が生きる上でなくてはならないものであると同時に、病気の不安と隣り合わせのサービスでもあります。異国の地であれば尚更、言葉の壁、費用面の不安、制度や文化の違いなど、不安が大きくなります。

「きちんとした医療通訳がいる」ということは、海外にルーツのある方が安心して病院を受診できるということにつながります。それは、病気が早期に発見・治療されるという意味で社会にとってもメリットがありますし、病院視点でも通訳ミスによる責任問題が発生するリスクを防ぐことにつながります。さらに、セサルさんのように、日本で暮らす海外ルーツの方たちの雇用につながる可能性も秘めています。
セサルさんは自らの経験を生かしてこの課題の解決に取り組んでいる、この日本社会にとってとても貴重な存在だと思います。ただ、まだまだ壁は大きそうです。医療通訳が個人の責任、そして子どもたちの負担となってしまっている日本の状況を少しでも変えていけるよう、医療機関や行政が協力して質の担保された「プロの医療通訳」を養成する仕組みを構築していくことが必要ではないでしょうか。